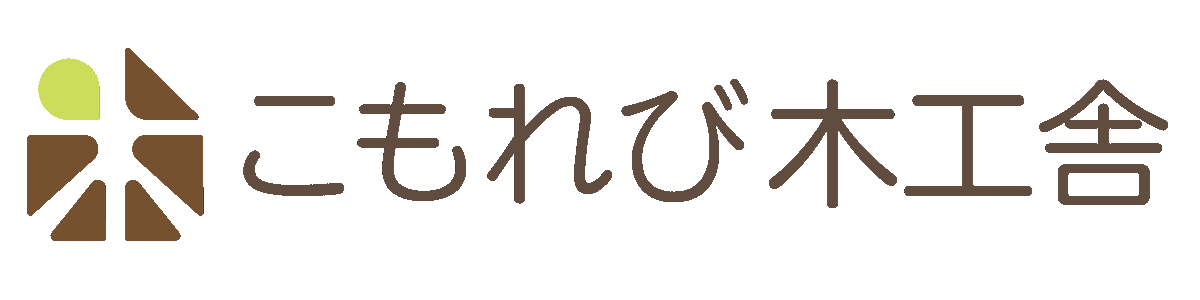「偽心材」
ニセのココロの材料と書きますので、あまりいいイメージは受けないかもしれません。
広葉樹の木部は、一般に、幹の中心に近い部分の「心材」、樹皮に近い部分の「辺材」で構成されています。
例えば、ホオノキの心材は濃い緑色、辺材は白い色をしていて、その違いは明らかです。
一方で、ブナの場合は、心材と辺材の区別は明確ではなく、全体が均質な淡いピンク色っぽい色合いに見えます。


写真は、新潟県魚沼市大白川で間伐したブナの木の切り口です。
中央の色の濃い部分が「偽心材」です。
ブナの木は、例えば大雪で枝が折れてしまったり、クワカミキリなどの虫の幼虫が内部に侵入するなどのストレスを受けたときに、その防御反応としてタンニンなどのフェノール類を作り出します。
フェノール類には木を腐らせる「腐朽菌」の繁殖を防ぐ働きがあり、細胞壁などに色素として沈着することで自らを守るのです。
いわば、「偽心材」はその木が生きてきた証とも言えます。
構造的な強度は通常の木部とほぼ変わりません。
模様や色味には個体差があり、自然が描いた一点モノのような魅力があり、スノービーチプロジェクトでは、この模様を「生態デザイン」と称しています。
大白川のブナ林で伐採される木のおよそ8割に「偽心材」があるとのことですから、むしろこちらの方が普通と言ったほうが良いかもしれません。
偽心材があるから、薪や木材チップにしかならないというのでは、なんとももったいない話です。
スノービーチプロジェクトのメンバーは、それぞれ偽心材をデザインに活かす取り組みをしています。
こもれび木工舎でも、MORRY GO ROUND ’25に合わせて、偽心材をデザインに取り入れた時計などを作ってみました。
色の濃い部分と薄い部分をどうデザインに取り入れていくのか…。
デザインセンスに乏しい私には大きな課題です(笑)